ねこから目線。とは
関西圏を中心に活動しているノラ猫・保護猫専門のお手伝い屋さんです。
サポートが必要なことがあれば、なんでもお気軽にご相談ください。
猫の保護活動や、殺処分の予防的取り組みとしてのTNR活動、地域猫活動、多頭飼育崩壊ケースなど猫が絡む問題への支援に取り組んできたキャリアのあるスタッフが対応いたします。
保護猫活動がすべてボランティア任せにならずきちんとした社会システムの中で機能する社会的企業となることでボランティアの負担軽減と保護活動のスピードアップと充実を図りたいと考えています。
STAFF
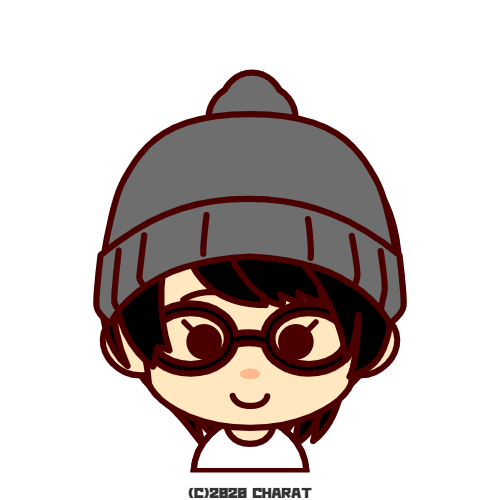
「猫の問題は、人の問題でしかない。」という視点から猫の問題を解決する目的で、立命館大学大学院応用人間科学研究科対人援助学領域に進学。猫を切り口に、共生と共存社会のリアリティについて研究し、2015年に修了。その後公益法人の勤務や大学での勤務経験を経て、2018年にねこから目線。を開業する。並行して、人もねこも一緒に支援プロジェクト(NPO法人)を立ち上げ、福祉的な支援が必要な家庭でありながらペット問題を抱えるケースに対して福祉機関と連携をしながら支援を実施する活動も行っている。
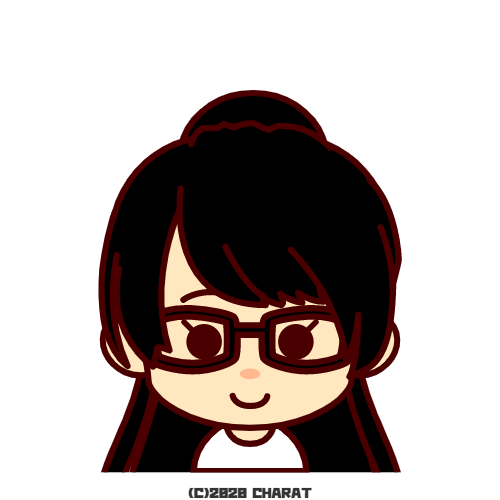
公益財団法人の動物保護施設にて10年勤務し、猫の飼育班のリーダーとして保護猫の飼育・譲渡を担当。2019年より、代表の小池からの熱烈なオファーを受け、ねこから目線。にジョインする。専任の現場スタッフとして、最前線で日々猫と向き合っている。
殺すのではなく生かす術を。これが、この活動の入口でした。感情的な批判だけでは何も改善しません。まずは、自分が出来ることを一つ一つ取り組みたいと思います。

動物看護士、トリマーの資格を有し、北摂TNRサポートのらねこさんの手術室で約3年勤務し、看護師業務2年、捕獲送迎業務に1年従事する。代表の小池からのオファーを受け、2022年9月より、ねこから目線。に移籍し、現場スタッフとして活躍している。
とにかく猫が好きで、猫に対してより密接に関われる場所に誘ってくださった小池さんに感謝しています!
猫について考え、知識を身につけて猫や猫に関わる方々の支えになりたいです。

30代半ばから個人事業主としてポスティング代行業を営む。自身が関わっていた野良猫のTNR及び怪我をした猫の捕獲救助をねこから目線。に依頼し繋がりが生まれる。
ねこから目線。から迷子猫チラシのポスティング代行依頼を受けるうちに猫の命にかける理念に影響を受け、現場スタッフへの転職を自ら志願する。
猫は自分で助けてと喋ることができません。猫の命の危機には人間が能動的に動くしかなく、まずは目の前の1頭を命の危機から救うために現場第一主義で行動したいと思っています。

2019年にお家に入ってきた野良猫10匹を保護をしたことをきっかけにTNR活動と保護猫活動に取り組んできました。
猫と人間の共生と幸せを願い、猫さんに寄り添い、出来ることを日々考え行動をしていきたいと思います。

幼少期、拾ってきた猫4匹と共に暮らす。
大学卒業後、精神科作業療法士として勤務。第二子出産を機に退職。
2018年、交通事故で倒れていた猫を保護したことをきっかけに保護猫活動に関心を持つ。以降、TNRと保護が必要な猫の譲渡活動に取り組む。
福祉と猫の問題に関心があります。また、語学が好きで英語とタイ語を少し話します。色々な方の架け橋になれれば嬉しいです。
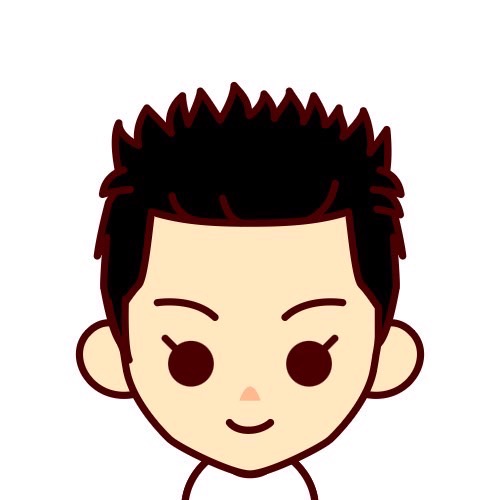
公益財団法人の動物保護施設にて4年勤務し、猫の飼育班のリーダーとして保護猫の飼育・譲渡を担当。
以前は目の前の猫達に必死になる日々でした。「ねこから目線。」の活動を知った事でより一層視野を広げ、たくさんの猫と猫を想う方々に貢献できるよう努めます。

短大卒業後約17年アパレルの販売職に従事。保護猫を迎えたことで野良猫問題に関心を持ち、野良猫の為に出来ることがないか模索している中、ねこから目線。の求人情報を見て飛び込みました。
猫について学びつづけ、猫も暮らしやすい世の中に近づけるよう精進します。
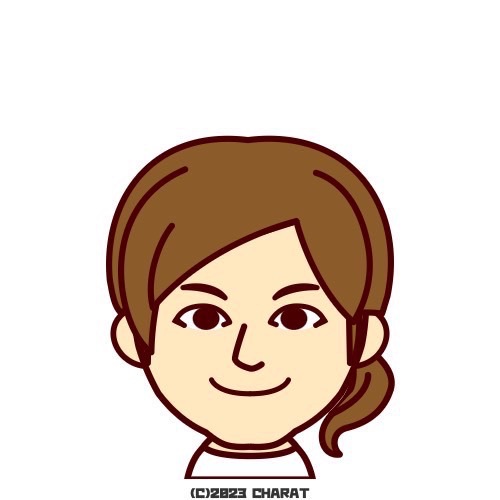
本業のかたわらで個人ボランティア、任意団体、NPO法人を立ち上げTNRや保護、譲渡、啓発活動を展開していましたが、コロナ渦を機にすべての時間をねこたちのために費やそうと決意。
決意とほぼ同時に「ねこから目線。」のFC展開の報せが飛び込んできました。やるしかない!と自分に言い聞かせてやっとスタート地点に立つことができました。
どのようなケースにおいてもていねいな対応を心掛けて参ります。
「ねこから目線。」の一員として、ねこと人が共生できる社会になるよう力を尽くしたいと思います。

北里大学獣医学部獣医学科卒業後、動物愛護センターや動物病院に勤務。
2021年1月に往診専門の『なぎ犬猫ワクチン往診所』を開院、2023年7月にTNR専門の『そとねこさんの手術室』を開院。
代表・小池との出会いをきっかけに、オーナーとして『ねこから目線。福岡久留米』の展開を決意。
本業の傍ら、保護猫活動も継続中。
「猫の殺処分ゼロ」という大きな目標を達成するため、今までできる事・必要な事を考え行動してきました。
ですが、まだまだやらなければいけない事が山積みです。
一歩一歩着実に、目標達成へ近づいていけるよう頑張ります。
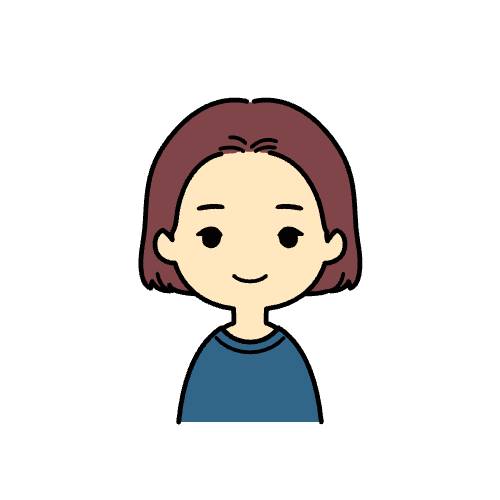
大学生の時に突然母が連れて帰ってきた猫さんが初めて猫さんとの触れ合いになり、
去年からなぎ犬猫ワクチン往診所の保護猫さんたちのお世話ボランティアに入ることで、保護猫さんと関わりを持つようになりました。
ねこから目線。福岡久留米発足を機に猫さんの為に活動する世界へ飛び込みました!
猫さんのために出来ることを頑張ります!

山口県出身。自身が産まれる前から家族に猫がいたことがきっかけで気づいたら猫が好きになっていた。
猫のためになにか出来ないかと、保護猫カフェのお世話ボランティアをする。ねこから目線。の勉強会に参加後、東京でのFCの話が上がり参加を即決。
とにかく猫が好きです。にゃーにゃー鳴くふわふわな毛玉が愛くるしくてたまりません。ねこと人が上手く共生できるように全身全霊でお手伝いしていきます。

鳥取で森としっぽ。のプロジェクトと、認定NPO法人人と動物の共生センター鳥取支部の運営に関わりながら、「人と動物が共に生活することで起こる社会的課題の解決」に向けて日々奮闘しているなか、私が師匠と慕っている先輩に、ねこから目線。の勉強会を教えてもらったのが、代表・小池との出会いでした。
森としっぽ。
https://www.instagram.com/moritoshippo/
人と動物の共生センター
https://human-animal.jp/
「猫の問題は、人の問題でしかない。」という視点から猫の問題へアプローチし、NPOのほうでは福祉機関と連携をしながらの支援と根本的解決を目指している、小池の掲げている理念や魅力にあれよあれよと引き寄せられ(笑)、この度パートナースタッフとしてジョインしました。
猫のためになること。猫のために、と関わるかたへの貢献。そして数字だけではない真の「猫の殺処分ゼロ」が達成できる日が来たら嬉しいです。日々スキルアップしながら頑張ります。

生まれも育ちも埼玉県。飼い猫3匹に癒される毎日を送っています。関東圏でペット探偵事務所を開設し活動。猫のため、困っている人のために。ねこから目線。の理念に共感し活動(関東)に参加。
寝て食べて寝て食べて…幸せそうに寝る猫の顔が大好き。猫に関わる人達がハッピーに。猫のお困り事、おまかせください。

岩手県出身。公務員をやっていたが直接人の喜び,幸せにもっと関与してみたいと思い退職。
猫から目線の活動を知り,感銘を受けたので参加。
人間と動物の共存について解決しなければならない事が多くある中,自分ができることを通じて他に影響を与えられるように,日々精進していきたいと思います。

フルタイムの本業をしながら、2020年から保護犬猫活動に興味を持ち、2022年に兄妹猫4匹を保護した事をきっかけに保護猫活動を本格的に開始。
世の中の猫達が幸せに暮らせるよう、保護活動や猫エイズの理解を深める啓発活動にも力をいれています。
東北の山形県で、猫のためになることをお手伝いしていきたいと思います!
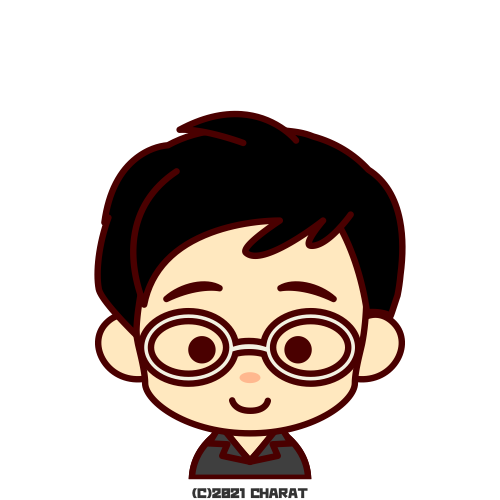
27歳で「世の中を編集する会社」アソブロック株式会社を設立。以降も、会社を「人が育つ場」だと見立て、業種・業態を問わず多くの法人を立ち上げ、自ら経営する。また、若手経営者の育成を目的に、他社の経営支援も行う。団遊ヨノナカ編集舎主宰
小池と梅本の「猫の殺処分をゼロにしたい」という熱い想いに打たれて参加しています。主にビジョン達成に向けた仕組みづくりを担当。
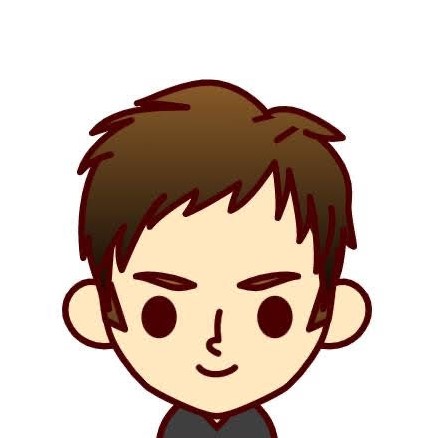

動物保護シェルターで10年、猫のスペイクリニックの立ち上げ運営をして7年、ずっと動物の現状を変えたいと生きてきました。そろそろ自分の人生にも様々な色付けをしたいと森の中の古民家に引っ越し、そこからフリーランスとして動物の現状を何とかする企業とNPOに参加中。
ねこから目線。は、1日でも早く猫の殺処分ゼロを達成するために様々な新規事業を通じて社会へアクションを起こし続ける企業です。それに関われるワクワクを日々感じてます。

大手流通小売業でのショッピングセンターの企画開発から社会人のキャリアをスタート、その後、フランチャイズ本部立ち上げのコンサルティング会社にて研鑽を積み、現在はフリーランスのコンサルタントとして、様々な新規事業や業態の開発に携わっている。
社会的企業である「ねこから目線」を、フランチャイズの仕組みなどによる多拠点展開をサポートしています。本部と加盟店双方の、Win-Winの関係づくりを進めて参ります
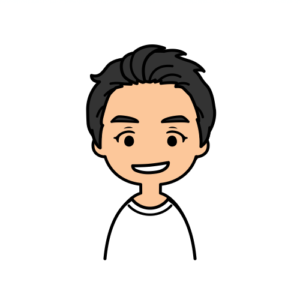
京都の大学を卒業後、東京の広告・メディア系ベンチャー(イシン株式会社)に就職。営業として、2年間365日オーナー経営者に会い続ける日々を過ごす。その後京都に一時的に戻り、公認会計士試験勉強に集中。3年後、東京の大手監査法人(有限責任監査法人トーマツ)に就職し、公認会計士試験に合格。2年半の監査法人勤務を経て、現在は会計・金融コンサルベンチャーに勤務する傍ら、ねこから目線で事業企画として活動中。
8年前、動物が苦手だった私を、一匹の赤ちゃん猫が変えてくれました。小さな命が両手の平の中で、愛らしくモゾモゾ動く感覚は忘れません。常に、世の中の素敵な面に着目していたい。猫ちゃん保護を通して優しい世界を!

大学卒業後、ラジオ局やネットベンチャーでのフリーター経験を経て大学院に進学。修了後大手広告会社に就職、いくつかの事業会社とコンサルティング会社へ転職するも一貫してマーケティングキャリアを歩む。ブランディングや広告・PRを中心とするマーケティングコミュニケーション戦略構築と実践が特に強い。
「猫の問題は、人の問題でしかない。」という視点に強く共感しています。知れば知るほど「猫の問題は、人の問題」。だれもの日常の中にあるとても身近な社会的な問題解決のために、ねこから目線。でチャレンジしたいと思っています。

群馬県出身。リクルートライフスタイル(現リクルート)契期満了による退社後、同僚と共に起業し、その後個人事業主として独立。様々な企業における集客や採用、認知向上の支援を行っている。
もともと猫が好きだったこともあり、「猫も人も幸せに」を心情として、SNS運用の側面から「ねこから目線。」のお手伝いをしています。

特定非営利活動法人どうぶつ弁護団理事長。民事・家事事件全般を取り扱いながら、ペットに関する事件や動物虐待事件を手がける。動物愛護管理法に関する講演やセミナー講師も多数。
ねこから目線。の事業を法律面からバックアップしてまいります。

目指せ虐待ゼロ!全国初の動物守る専門家チームに密着(ABCテレビキャスト 特集番組)
罪なき猫が犠牲に・・・一体誰が?保護の現場に密着(ABCテレビキャスト 特集番組)
猫専門のお手伝い屋さん「ねこから目線。」代表の小池英梨子さんインタビュー(アイデアニュース)
猫にメリットがあることなら何でもお手伝いします! ノラ猫・保護猫専門の『ねこから目線。』(まいどなニュース)
まいどなニュース関連記事(1)
まいどなニュース関連記事(2)
さくらねこブログ(フェリシモ猫部 猫ブログ)
ねこから目線。活動紹介 ネコリパブリック代表河瀬麻花 X ねこから目線。代表 小池英梨子 トークセミナー at 猫助け文化祭みのおキューズモール with ピュリナ
代表小池の連載より
49号「考え改め、迷子猫に力を注ぐ」
47号「ねこから目線。株式会社になる」
42号「ねこから目線。開業2周年」
38号「ねこから目線。開業1年を振り返って」
36号 「社会的企業について」
代表の小池が対人援助学会のwebマガジンに連載してるバックナンバーはこちら
医療アドバイザー

橋本恵莉子 獣医師(Happy Tabby Clinic 医院長)
早期不妊手術や、生き物への愛護精神を育む為の教育を推進する獣医師。医療アドバイザーとして相談に乗っていただいています。
第一種動物取扱業者標識

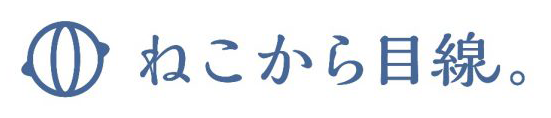
常に、考え続け、問い続け、行動し続けていきたいと思っています。対人援助学会発行、Web無料マガジン「対人援助学マガジン」連載しています。連載タイトル「そうだ、猫に聞いてみよう」21号から連載開始